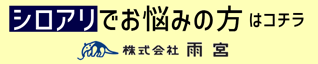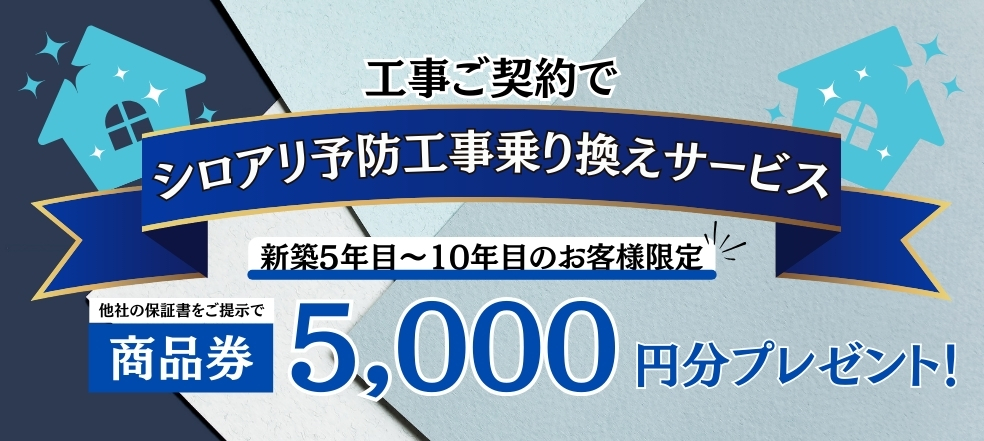雨宮の無料床下診断を。
お問い合わせはこちらから
お問い合わせフォーム
「床や畳が湿っている」「部屋の中がジメジメする」など、住宅内の湿度の高さが気になっている場合、床下の湿気対策が必要になるかもしれません。
床下に湿気がたまると、木材が腐食するほか、カビや害虫が発生しやすくなるなど、住宅や健康に害を及ぼすことがあります。
この記事では、床下に湿気がたまる原因から、湿気対策が必要な家の特徴、また湿気対策を怠った場合のリスクや自分でできる湿気対策まで、わかりやすく紹介します。
床下に湿気がたまる原因

湿気がたまる原因には、次のような要因が挙げられます。
- 通気性が悪い
- 床下に水が入り込みやすい
- 土地の性質
例えば、住宅の基礎部分に設けられた換気口の前に物を置いていると、風通しが悪くなり湿気がたまりやすくなります。
また、住宅の敷地が周囲の土地よりも低く雨水が流れ込みやすいなど、地形的な要因によって湿度が上がるケースもあるでしょう。
土地の性質も湿度に大きく影響します。もともと田んぼや湿地帯だった土地は、土壌に含まれる水分が多いため、床下の湿度も上がりやすい傾向にあります。
床下の湿気対策をしなくてもよい家

床下部分をコンクリートで覆った「ベタ基礎」工法の住宅は、厚いコンクリートと防水シートが仕切りとなり、床下空間に湿気がたまりにくいのが特徴です。
蒸発した水分が建物に伝わりづらいため、地面がむき出し、あるいは床下を覆うコンクリートが薄い「布基礎」のように、積極的な湿気対策は必要ありません。
ただし、雨季や夏場になると、コンクリートの打設に関係なく床下湿度は上昇します。
ベタ基礎でも、築10年ほど経つと床上部分の木材にカビが発生するケースもあるため、ある程度の湿気対策は必要です。
また近年の住宅は気密性や断熱性が高く、年間を通じて快適に過ごせる反面、家の中に湿気がこもりやすいということも忘れてはならないでしょう。
床下の湿気対策が必要な環境
床下の湿度が上昇しやすい家は、立地環境や土地の性質、建物の構造などが起因している場合があります。自身の自宅が当てはまるかどうかチェックしてみましょう。
- 敷地が周りの土地に比べて低い位置にある
- 水田や湿地を造成した土地
- 床下の空間がせまい
- 住宅密集地
- 台風などで床下浸水にあったことがある
敷地が周りの土地に比べて低い位置にある
住宅の敷地が、周囲の土地や道路よりも低い位置にあると、大雨や台風などの自然災害時に雨水が床下に流入しやすくなります。
また、山や丘のふもとに建てられた住宅も、上流から流れてきた水が滞留しやすいため、床下に湿気がたまりやすいです。
流れ込んだ雨水を放置すると、蒸発しきれなかった水分が床下にとどまって、室内の湿度が上昇したり結露の原因になったりすることがあります。
水田や湿地を造成した土地
田んぼや沼地などの湿地を宅地に転換した土地は、通常の土地よりも土壌の水分量が多い傾向にあります。
造成工事が十分におこなわれていれば、それほど心配する必要はありませんが、何らかの事情で地盤改良などが不十分だった土地は注意が必要です。
土壌の水分が蒸発して住宅全体の湿度が上昇しやすいため、湿気対策を怠ると、木材の腐食やカビの発生に繋がるケースがあります。
床下の空間がせまい
床下の空間がせまいと、風通しが悪くなり湿度が上昇しやすいです。
現在の「建築基準法」では、木造住宅の防湿措置として、地盤から床上面までの高さを45センチメートル以上にすることが義務づけられています。
一方、基準法が制定される1950年以前に建てられた住宅は、床下に十分な空間を設けていないケースも多くあります。
床下に十分な空間がない住宅は、積極的な湿気対策が必要でしょう。
参照:建築基準法
住宅密集地
隣家との距離が近い住宅密集地は、風通しがよくないため、よどんだ空気とともに水蒸気が滞留し湿度が上がりやすくなります。
また密集地の中でも、建物の陰になる日当たりの悪い住宅や、ブロック塀でしっかりと囲まれた住宅などは、特に湿度が上昇しやすいです。
排水対策がしっかり整備されていても、雨が降って床下に湿気がたまると、カビや結露の原因になりやすいため、年間を通じた対策が必要となります。
台風などで床下浸水にあったことがある
住宅付近に河川があり、台風や豪雨などで床下浸水の被害が想定される住宅は、災害後に十分な湿気対策をおこなう必要があります。
床下の乾燥が不十分だと、木材が腐食したりカビや悪臭が発生したりするなど、生活や健康面に大きな影響を与える可能性があるからです。
また湿気を放置すると、湿度の高い場所を好むシロアリなどの害虫が発生しやすくなり、木材を食すことによって建物の耐震性を損なう恐れもあります。
床下の湿気対策を怠るとどうなる?
床下の湿気対策を怠ると、快適な生活を送れないだけでなく、家の寿命を縮めてしまう原因にもなります。ここからは床下対策を怠った場合にどうなるのかを解説します。
木材の腐食

床下の湿気対策を怠ると、腐朽菌が発生し木材を腐食させることがあります。腐朽菌は、木材に含まれるリグニンやセルロースを分解し劣化させるのが特徴です。
腐朽菌は、酸素と栄養分のほかに湿度が85%以上で木材に含まれる水分量が25%以上、また温度は20度から30度という条件のもとで旺盛に繁殖します。
腐食を放置すると、共存関係にあるカビが繁殖したり、家の耐震性が低下したりする恐れもあるため、床下の湿気対策は欠かせません。
| 腐朽菌の繁殖条件 | |
|---|---|
| 酸素 | 栄養を取り込む際に必要 |
| 栄養分 | 木材の主成分(セルロース・リグニン・ヘミセルロース) |
| 温度 | 20度~30度(最も繁殖しやすい) |
| 水分 | 湿度85%以上、木材の含水量25%以上 |
腐朽菌の繁殖条件である、酸素や栄養分、温度を管理するのは難しいですが、水分(湿度)は唯一対策が可能です。
カビが生える

カビも腐朽菌と同様に、栄養分や酸素、適度な温度に湿度などの条件が揃うと発生します。特に、高温多湿になりやすい床下はカビの増殖に好都合の環境です。
カビは湿度80%以上の環境で繁殖しやすいと言われていますが、実際は空気中の水蒸気ではなく、木材などの表面に付着した水分を使って繁殖します。
また、カビは悪臭の元になるだけではなく、アレルギーや気管支炎の原因になるなど、健康面に悪影響を及ぼすケースも少なくありません。
参照:(株)衛微研
シロアリなどの害虫が発生する

高温多湿を好むシロアリやダニ、ゴキブリなどの害虫が発生し、人や住宅に被害を与える場合があります。特に、木材を栄養源にするシロアリの食害には注意が必要です。
床下の湿気に誘われたシロアリが、住宅の基礎部分や柱などを食い荒らし、家の耐震性を低下させる恐れがあります。
シロアリは、おもに人目につかない木材の中で生活しているため、知らない間に食害が拡大するケースも少なくありません。
シロアリによる被害が拡大していないか心配な場合は、害虫駆除に精通した専門業者に相談することをおすすめします。
住環境や家の寿命に影響が出る
床下に湿気が溜まると、住環境や住居の寿命に影響を及ぼす場合があります。湿気をそのまま放置すると、ダメージは床下だけにとどまらず、家全体に広がりやすいです。
床や壁を伝って腐朽菌が家中に繁殖すると、床のきしみや木材の腐食、カビの発生などを引き起こし、快適に生活できなくなる場合があります。
また、壁や床の断熱材が湿り気を帯びると、断熱の効力が薄れて十分な断熱効果を発揮できません。
場合によっては、住宅の耐震度が低下して最悪の場合、災害時の倒壊に繋がる恐れもあります。
自分でできる床下の湿気対策
床下の湿気対策として自分でできることをいくつか紹介します。
換気口を掃除する
床下の風通しを確保する換気口や、その周辺を小まめに掃除しましょう。
建築基準法では、防湿措置として壁の長さ5メートル以下毎に、300平方センチメートル以上の換気口を設置することが義務づけられています。
この換気口をふさぐように、植木やエアコンの室外機などを長期間置いていたり、ゴミが溜まっていたりすると、床下の湿度が上昇しやすくなってしまいます。
普段から、換気口の前に除湿を妨げるような物は置かないようにして、詰まっているゴミなどは定期的に取り除きましょう。
参照:建築基準法施行令
床下に木炭を敷く
多孔質で吸着性のある木炭は、水分を吸収する除湿効果に優れています。
(財)日本木材総合森林センターによると、実際に人が住む木造住宅を使った研究で、木炭は床下の湿気対策に一定の効果があると結論づけています。
木炭を敷いていない床下の木材の含水率は19%から24%でしたが、木炭を敷いた木材の含水率は14%から20%でした。
ただし、木炭が常に乾燥した状態でなければ大きな除湿効果は狙えません。3ヶ月から半年に1度は天日干しをして、しっかりと乾燥させる必要があります。
湿気対策を業者に依頼した場合の費用目安

「自分では対策が難しい」「根本的に解決したい」という場合は、湿気対策に精通した専門業者に依頼することをおすすめします。
業者によって前後しますが、目安となる費用相場は次の通りです。
【専門業者に依頼した場合の費用相場】
| 設置メニュー | 費用相場 |
|---|---|
| 床下換気扇 | 2台~4台目安(30坪当たり) 総額10万円~25万円 |
| 床下防湿シート | 約1万円(1坪当たり)総額10万円~20万円(一般的な戸建て) |
| 床下調湿剤・調湿マット | 約1万円~3万円(1坪当たり)総額10万円~30万円(一般的な戸建て) |
床下の通気を良くする「床下換気扇」は、30坪(約100平方メートル)の住宅なら、2台から4台の設置が目安で、配線を含む施工価格は10万円から25万円程度です。
月々の電気代と定期的なメンテナンスは必要ですが、ランニングコストはさほどかかりません。
地面の湿気から住宅を守る「床下防湿シート」は、敷き込み工事費(防湿シート費込)が1坪あたり約1万円で、一般的な戸建て(30~40坪程度)であれば10万円から20万円程度が相場です。
また、床下の湿度をコントロールする「床下調湿剤」や「調湿マット」は、坪単価が約1万から3万円、戸建て1件当たり(30~40坪程度)10万円から30万円ほどかかります。
調湿効果は半永久的で、防湿シートの役割も兼ねる調湿マットであれば湿気の調節に加え、湿気のシャットダウン効果も狙えます。
まとめ

敷地が周りの土地より低く地形的に雨水が流れ込みやすい、あるいは風通しが悪い環境にある住宅は、床下の湿気対策が必要です。
対策を怠ると、木材の腐食やカビの発生だけではなく、住宅の木材を食するシロアリなどが発生する恐れもあるため、早めに対処する必要があります。
床下の湿気対策は自分でも可能ですが、対策が難しい場合や根本的な解決を希望する場合は、専門業者に相談してみるとよいでしょう。
この記事の監修者

犬飼 章博
- 2015年 最年少で豊橋支店長就任
- 2021年 本社支店長就任
- 2023年4月より愛知県しろあり対策協会理事
住宅のシロアリ調査から始まり、その他の様々な害虫対策や防水・断熱といったリフォーム工事全般を経験してまいりました。調査実績は延べ数千件以上。
本社の支店長になっても現場が好きで、今も前線で活動しております。
疲れた体を癒すため、趣味は温泉巡りです。
- 資格
- しろあり防除士
- 一級建物アドバイザー